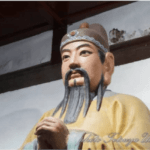関羽の武威が中華を震わす・・・劉備軍の「樊城攻め」は、なぜ大失敗に終わったのか?
ここからはじめる! 三国志入門 第121回

219年、関羽の樊城攻め想像図 ※当時の正確な地形は不明のため、川筋や地形は現代のもの。布陣図は正史の記述をもとにイメージで構成/地図作成・ミヤイン
■あせった曹操は遷都を検討、次々新手を投入
重要拠点の危機をさとった曹操は、援軍を次々に派遣する。その第一陣が于禁(うきん)と龐徳(ほうとく)であった。于禁は軍歴30年のベテラン、龐徳は西涼の猛者。いずれも百戦錬磨だが、折からの長雨で川の水が増水し、彼らの軍勢(呉主伝に3万とある)は水没してしまう。
これを見た関羽は水軍を駆って二将を捕らえ、武勇を改めて天下に知らしめる。恐れをなした曹魏勢力のなかから関羽に降るものもあり、知らせを受けた曹操以下、中原の者たちは震えあがった。「羽の威、華夏(かか/中華)を震わす」(羽威震華夏)と関羽伝は述べる。
樊城から許都まではそう遠くない。あせった曹操は遷都まで考えるが、参謀の司馬懿(しばい)らがこれを押しとどめ「孫権に関羽の背後を襲わせましょう」という。この一言で戦の風向きが変わった。曹操の求めに応じた孫権は、呂蒙(りょもう)に江陵を攻めさせる。
曹操は第二の援軍を派遣。切り札ともいえる名将・徐晃(じょこう)である。徐晃の軍は新兵が多かったが、樊城の北方にある陽陵坡(ようりょうは)で副将の徐商、呂建が合流し、関羽の包囲軍を攻撃した。
徐晃は関羽軍の退路を断つ構えで陽動作戦を展開し、偃城(えんじょう)を奪回。さらに関羽軍の陣営(囲頭・四冢)を攻撃する。2つある陣営のうち、片方を攻撃すると見せかけて、もう片方の攻略にかかったのだ。
徐晃の巧みな用兵術の前に、関羽の鉄壁の包囲陣は崩壊しはじめる。関羽軍はすでに出陣3か月。長期戦で兵の疲れも出ていただろう。これに追い打ちをかけたのが「孫権裏切り」の一報だ。徐晃は樊城の内外へ矢文を射込み、それを知らせた。城内が沸き、城外の関羽軍に動揺が広がったのはいうまでもない。
■孫権の裏切りと樊城攻撃への影響は?
北伐の失敗の原因は、関羽の荊州統治や孫権との外交にもあった。これについては、今回は長くなるため詳しく述べない。ともかく、孫権があっさりと「寝返った」ことが劉備サイドにとって痛恨だったわけだが、問題なのは「孫権が裏切ったから関羽は負けたのか?」「裏切らなければ関羽は樊城を取れたのか?」ということだ。
実のところ、孫権の裏切りとは関係なく、関羽の北伐は破綻を見せ始めていた。樊城は長雨の影響で城壁の大半が水没するところまで追い込まれていたが、降伏開城の兆しはない。城内にいる参謀の満寵が降伏論を押しとどめ、曹仁に踏ん張らせていたからだ。ここまで持ちこたえるのは、関羽にとって想定外だったかもしれない。
さらには曹操から増援の第三陣が派遣され、徐晃の軍はさらに数を増した。孫権との密約を結んだことで、東方の揚州の守備兵を荊州へ動員できたばかりか張遼(ちょうりょう)までが、この戦線に加わるべく出陣している。ただし、張遼の軍が辿り着くまえに決着はついてしまった。
かくして兵力・士気ともに勝る徐晃軍に押される一方となった関羽は、ついに樊城・襄陽の包囲を解き撤退した。閏10月、そのとき孫権軍が本拠地江陵にまで侵攻したとの報が入る。あわてて軍を返す関羽だったが、辿り着く前に江陵・公安は孫権軍の手に落ちていた。
退路を断たれ、西の麦城(ばくじょう)に拠った関羽だったが、すでに江陵が落ちたと知るや、兵の大半は四散してしまった。関羽は降伏すると見せかけ、益州へ逃れようとするも、待ち構えていた呉の大軍にあえなく捕らわれる。一代の英傑の最期であった。
〈次ページ〉関羽はなぜ敗れたのか